侵害防止調査の具体的な方法 調査範囲の決定方法
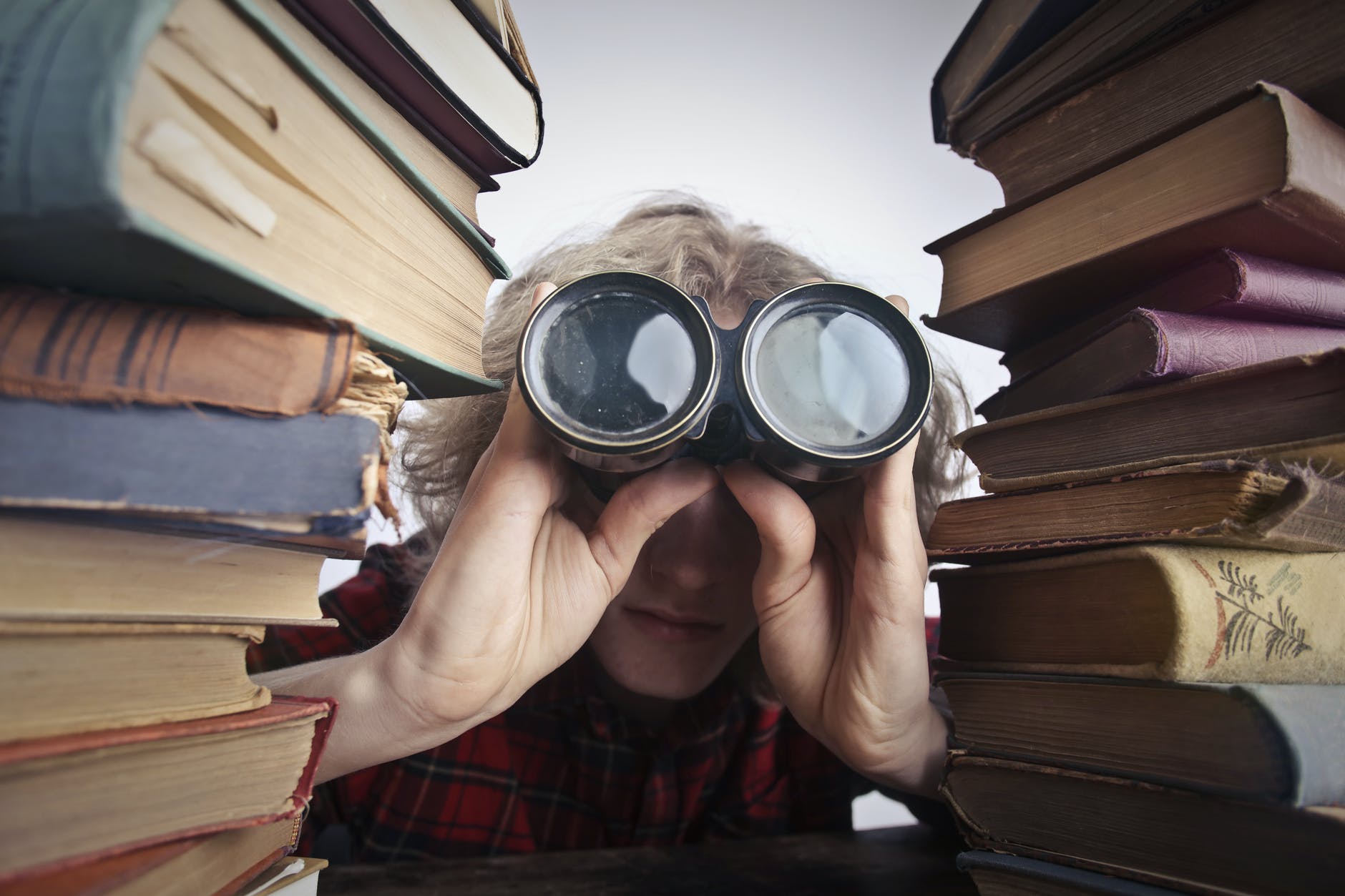
侵害防止調査の具体的な方法 調査範囲の決定方法
特許の侵害防止調査(スクリーニング調査)を実際に自分でしたことがあるという人は少ないと思います。
規模の大きな企業であれば知財部に丸投げであったり、専門部門が無い会社の場合は外注に出したりといったケースが多くなります。
しかし、侵害防止調査を自分ですることで新たに気付けること、周辺技術の状況等有益なことも多くあるので、今回は侵害防止調査をする際の具体的な方法について書いていきます。

侵害調査は、割合に難易度が高いです。
調査対象とする特許分類を決める方法
侵害防止調査に求められるのは極力漏れがないように調査することです。漏れがあると「侵害している特許権がない」と思って安心していると、突然に警告を受ける可能性が高いため、漏れは許されません。
キーワードだけで検索をかけていると多くの検索もれが生じる可能性が高いので、特許庁が設定している特許分類を使って調べる事が有効な手段になります。キーワードだけですと、人によって使う言葉や表現の仕方が違うのでうまく検索できないためです。
分類(FIやFターム)を使うことは必須です。
具体的にはFI、Fタームという分類を使った検索をすることになります。FIとは国際特許分類をより詳細に分類したもの、Fタームは違う切り口で特許を分類したものとなっており、特許が出願されると特許庁でFI、Fタームが設定される仕組みになっています。
侵害防止調査においてどの特許分類を調査対象とするべきかを決めるときの具体的な方法を順序を追って説明します。
1.キーワード検索で近い出願を複数件ピックアップする
まずは調査対象を請求項に限定してピンポイントで近い公報を検索します。この検索においては全く同じ技術を見つける必要はなく、近い構成の出願や同等の課題を解決する出願から近いものを探します。この検索は、分類を決めるための予備的なものなので、抜けがあっても大丈夫です。
2.ピックアップした公報に設定されているFI 、Fタームを確認する
ピックアップした公報に設定されているFI、Fタームを確認するために、メモやエクセル等にそれぞれのFI、Fタームをメモしていきます。使用されているFI、Fタームのうち、特に近い技術に使われているFI、Fタームをピックアップしたり、予備検索で多く使われているFI、Fタームをメモしたりしておきます。
3.そのFI、Fタームが調査対象として的確か検討する
企業の知財部などに所属しており、自分が良く使うFI、Fタームであれば調べないでも知ってるという人もいるかもしれませんが、ほとんどの人はFI、Fタームを見ても技術分類はわからないと思います。
その場合には特許庁の特許検索サイト(J-PLATPAT )で特許分類を確認することができます。「特許・実用新案分類照会(PMGS)」のフォームに、メモしておいたFIやFタームを入力・検索して内容を確認します。そうすると、具体的に、分類の意味・内容を知ることができます。
調べてみると今回調べたい技術には関係ない分類が設定されていることもあるので、関係ない分類は削っていきましょう。きちんと読んでいく必要があります。
また、一つの特許分類だけリサーチすれば大丈夫ということはほぼ無いと言えますので、関連する技術分類が複数挙げられる場合はそれぞれを候補として残してください。
FIを複数確認すれば安心という場合もありますが、FIの内容も確認した方が良いケースもあるので技術分野に応じて適切な分類を選んでいきましょう。
4.FI 、Fタームの件数が多すぎる場合にキーワードや分類×キーワードで件数を絞る検討をおこなう
この分類に含まれてそうというものを全部出していって総件数を確認して全部見れる件数だと判断できれば全部を確認すれば良いですが、1万件を越えるような現実的な件数に収まらないこともあります。
その場合は分類にキーワードをかけて絞ることや、分類に分類をかけて絞るべきかを検討していきます。
絞る際にも今回の調査で関連出願が出る可能性が高い分類は全件スクリーニングして、念のため見ておきたい分類にはキーワードをかけるといった方法で検索もれとなるリスクを減らす工夫が必要になります。
かけ算をして件数を減らすということはその分検索もれのリスクを増やすことになるのでバランスを考えて行ってください。
また、侵害防止調査という性質上出願から20年が経過している特許については問題となる可能性は無いと考えてよいため出願から20年以上経っている特許は調査対象から除外しておきましょう。
まとめ
以上の方法で侵害防止調査をする際の調査範囲を決めることができます。
件数としては1000件以上の全件をスクリーニング調査しないといけなくなる場合がほとんどだと思ってください。

1000件の公報を読むのはたいへんですが、がんばりましょう。
大変な調査になることになると思いますが、しらみつぶしに全件を見ることで得られる気付きもあるかもしれないので前向きにスクリーニング調査をして侵害防止調査をしていってください。
今回は調査範囲の決定方法について書いたので、次回はどのような点に注意してスクリーニング調査をすれば良いかについて書いていきますのでそちらの記事も合わせてご確認ください。

